じょう舌な人って、会話やコミュニケーションが上手な印象がありますよね。
また、弁が立つ人も話に説得力があり、かっこ良さ、リーダーシップを感じます。
しかし、これらの魅力はプレゼンや会議などビジネスの場面では大いに発揮されますが、
親睦を深めたい相手や、日常のコミュニケーションにおいては、仇ともなりかねない側面があるのです。
私は長年の接客の経験から『日常会話において多くの人は、他人の話には大して興味ない』…ということを度々ここに書いています。
なのに人はそれと裏腹に『自分の話を喋りたがるという』なんとも不毛な現象が日々そこらじゅうで起きているわけです。
今回紹介する3つのNGな会話は、コミュニケーションにおいて、人が好感度を上げたいがためにやってしまう『賢さのアピール』が主たる原因と言えます。
賢さのアピールと言っても、
「僕は東大卒でして~」
「私、実はメンサ会員でして~」なんて大それた自慢ではなく、
『目の前のあなたたちより聡明な存在』
『このコミュニティの中で頼れる存在 』という、その場での存在意義を誇示するようなものです。
誰しもが少なからず持っている性質です。
しかし、特に関係性が発展途上にある相手には、賢さが伝わるどころか、ただ面倒くさがられるだけという結果になりかねない、そんなNGな会話についてのお話です。
ぜひ、接客、営業、職場、人間関係の構築の一つにお役立てください。
NGその① 知識の披露
知識とひとことに言っても、学識的なものから趣味までいろいろとあるので内容にもよるのですが、知識の多い人って、経験豊富で頭が良さそうなイメージは確かにありますよね。
知識が豊富であることは当然、会話に有利に働くこともあります。
ただ、その知識を欲しがっていない人に熱心に語り続ければ、需要と供給がアンバランスとなります。
そんな、知識をひけらかす人の裏面には
『経験豊富な賢い人間だと思われたい』
『自分はその筋において優れた人間だと思っている』
などどいうような特徴があります。
ですから、相手の為ではなく、ほぼ自分のためにやっていると言っていいと思います。
基本的に、人はみんな、自分の知っていることを教えたい性質がありますから。
知識を披露することの一体何が相手を不快にさせるか?ということを考えると、
興味のない(求めていない)話を 『上から目線』『自慢げ』に話されることと、
そして、いわゆる『にわか』『知ったかぶり』などが問題なのではないでしょうか。
「ネットで知ったような話を実体験のように言うなよ」
「たいしたネタでもないのになんでそんな誇らしげなんだよ」
っていう…
とはいえ、得意ジャンルの話になったとき、話を盛り上げるためにも言いたいネタってありますよね。
すっごく言いたいですよね。
そんなとき、知識の押し売りにならないような話し方の工夫も必要です。
まず私たちが得た知識の元は、大きく分けて実体験から得たものか外部からの情報のどちらだと思います。
・実体験 = 言葉の通り自分の経験に基づくもの。
・外部からの情報 = 人、テレビ、本、ネットなどから収集したもの。
どちらにしても、知識の押し売りは誰も好みませんが、
先ほど挙げた『上から目線』『自慢げ』『にわか』『知ったかぶり』を感じさせないよう、以下のような話し方が重要になってきます。
①熱心に語らない
②長々語らない
という基本的な作法のもと、もう一つポイントは、
③実体験と外部からの情報を分別した話し方です。
例えば、
「ポテトサラダの隠し味に砂糖を入れるとまろやかになる」という知識を
実際に経験した人が言うから「へー」となるのに対し
たいして料理経験もない人が「そういうものだ」と、これを言っても、
聞いている側にはただただ “信憑性のない話を自慢げに話をする人” に映り、信頼はおろかコミュニケーションすら抵抗されかねません。
でもここで、 “経験” と “外部からの情報” を分別して話すだけで、たいして料理経験のない人でも内容の信頼度が上がります。
「料理人から教えてもらった」
「私の母はいつも砂糖を入れると言っていた」
「以前、テレビでやっていた」
こんな風に話せば、上から目線、知ったかぶり感をなくし、ひとつの情報として受け入れられやすくなります。
知識は話を盛り上げるネタとして活躍するときもありますが、面倒臭さも持ち合わせています。
話すときはそんな工夫を心がけると良いと思います。
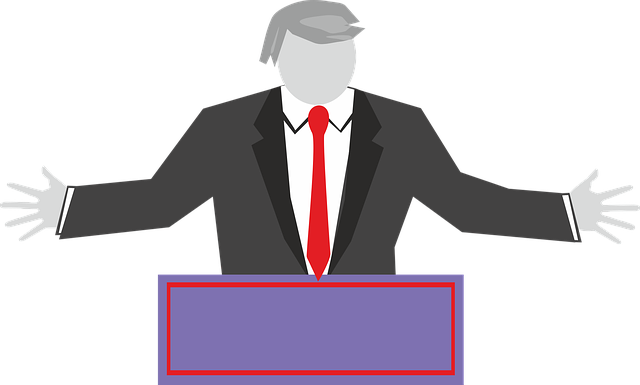
NGその② アドバイス・正論
アドバイスする人や正論を言う人…
アドバイスの必要性って本来、相手が指南を求めてきた時に初めて発生するものです。
「このお肉、どうしたらこんなに柔らかくなるんですか?」
「これは4時間煮込んでますが、ご家庭では圧力鍋で余熱調理でも…」
「彼女に嘘がバレそう。何て言い訳したら逃げ切れるかな?」
「また嘘を重ねてしまったら余計に大変なことになるのでは」
こんな具合です。
人はアドバイスが本当に欲しいときは「どうしたらいい?」「どう思う?」など「?」がついた質問形式で投げてきます。
ようするにQ&Aです。
なのでそれ以外は、相手は答えを必要としていないと思っていたほうがいいです。
言いたくなっちゃいますけどね。うだうだしていたり、何かに迷っていたり、煮え切らない様子の人には特に。
でも、自分が有益だと思う助言は相手にとっても有益とは限らないのです。
悪いパターンがこれです。
「会社の方針がちょっと古くてやってらんないんだよね…」と会社員が漏らしたグチに対し
「意見をはっきり言ったほうが会社のため」
「古いことが悪いんじゃなく、あなたとの相性が悪いだけ」
「新人ならとりあえず3年は我慢したほうがいい」
いやいや、べつに質問してない(答えも正論も求めてない)んですけど…みたいな。
もう一つ厄介なのが、アドバイスの親戚にあたる “自分だったらこうする” です。
「自分なら会社をこう変えていく」
「私ならすぐ他の仕事を探す」
「私が以前、職場に馴染めなかった時はあーしてこーして~」
いや、だからあなたがどうするかを聞かされても…ですよね。
頼まれてもいないのにアドバイスや正論を言う人は、相手のためではなく、これもまた自分のためなんです。
誰かが出せない答えを出すことで自分の賢さを高めることができるし、相手の役に立つという貢献欲も満たされる。そうすることによって気力やモチベーションも上がるからです。
しかし逆を言えば、
好きな人や、関係性を構築したい相手には、
その相手からアドバイスをもらうように会話を運ぶと、相手の気分を良くすることができるので、
そっちにシフトするのもコミュニケーションとしてはおすすめです。
接客にストレスを感じる方。よろしかったらこちらをどうぞ。
接客業のストレス。接客に疲れない方法。接客ストレスを増やさないために大切なこと。
NGその③ 自覚のない否定
否定と言うと、そりゃ言うまでもなくダメだろ…と思うでしょうが、
否定ばかりしている人は、否定ばかりしている自覚のない人であることがほとんどなんです。
まず否定って、どこまでが良くてどこからがNGなのか難しいかもしれませんが、
例えば『暴力は良くない』『歩きスマホは危ない』など法に触れるもの、確固たる倫理、または物理的に明確な答えがあるもの…以外は否定しない方が無難ですよね。
否定的意見はこれも “賢く見られる” …と思っている人がやりがちです。
「あの店のケーキはクリームが美味しい」より
「あの店のケーキはクリームが良くない」と言えば、ちょっと味がわかる人みたいじゃありません?
「あの法案は混乱を招くだけ」
「この絵は色彩バランスがまるで素人」
そのジャンルの知識にとても長けているように聞こえますよね。
自分は厳しい目や鋭い意見を持つ人間だ!という、賢さのアピールをしています。
このタイプは “否定する” というよりは 『悪いものや欠点をズバッと見抜く』という感覚が強いので、ネガティブな言葉の多さに気付いていないと思われます。
しかし、ネガティブな言葉というのは、聞いているほうにはしっかりと耳に入ってくるのです。
ほら、よくテレビでスポーツなんか見ていて、プロたちのプレーに
「ここで右に出ないからダメなんだよ!」「なんでここで決めないかなぁ!」
と、監督ばりにダメだしする人いませんか?
ファンとして熱くなるのは一定の理解ができても「じゃあお前が優勝させてこい」って言いたくなりますよね。
こういう人は、知識が豊富そうに見えて実は、限られたプレー技術の知識しか持ち合わせていないのでしょう。
本当によく知っている人はそのプレーの難しさまでも理解しているのですから。
こんな風に否定は、残念ながら相手にただ不快感を与えているだけで、賢い人だなんて思われていないわけです。
コミュニケーションにおいてはできるだけ肯定の言葉を心がけたいものです。
まとめ
・知識の披露
・アドバイス、正論
・自覚のない否定
自分がやられたら面倒くさいのに、
自分は、好感度のため、賢さのアピールのためにやってしまっているという悪循環。
思い返すと、意外と自分もやっちゃってるかも…と思った方もいらっしゃると思います。
私もついつい口を出してしまうこともありますが、
・自分の話が相手にとって面白いものとは限らない、
・話している自分が1番気持ちいいだけ
ということを思い出しては、コミュニケーション会話に工夫をこらしています。
こんな記事も書いています。
接客業必見!「褒めるより喜ばせる言葉」3つ。誰でも使える飲食店経営者の接客会話術。








