前回話、【顧客心理から考えるメニュー決め4つの法則!客単価UPラインナップ!居酒屋・ダイニングバー集客】にて、メニューを考察するときの法則みたいなものをお話しましたが、それに続き今回は、
顧客心理から『思わず頼みたくなる、売れるメニュー表の作り方』について考えていこうと思います。
さて、
お客様がご来店されてオーダーに伺ったとき、時々こんなやりとりありませんか?
客「ビール2つと…あと、おすすめってなんですか?」
店「当店は牛カツが人気ですよ。日替わりですと今日は熊本の馬刺しと、あと朝採りのアスパラも大きくておすすめです」
客「うーん… じゃあとりあえずモツ煮と生ハムサラダで!」
…もちろん、おすすめを聞かれたからって、気がすすまなければ注文されないのは当然のこと。それはわかっているんですよ。
おすすめを聞いてくるお客様は、何を食べればそのお店の味がわかるか本当に知りたい人もいれば、挨拶程度やコミュニケーション感覚で聞いてこられる方もいらっしゃいます。
どちらもありがたいことではあるんですけど、まぁちょっとだけ本音を漏らすと、そんな不毛なやり取りにモヤモヤすることもあるんです。
時には、お客様からも
「聞いたからには何か頼まなきゃ」
「せっかく説明してもらったのに頼みたいものがない」
みたいな、微妙な空気感が漂うこともあります。
飲食店のあるあるのひとつだと思うんですよね。
おすすめされたものに興味を持ち注文されるお客様もいますが、あまりに推されると心的圧迫感を感じたり、自分の選択権が狭められているように感じてしまうお客様もいらっしゃるわけです。
そんなわけで今回は
・お客様が自分の気分やタイミングで選択できて
・店側も、食べていってもらいたいものをアピールできる
これを解決するメニュー表の作り方のコツ、おすすめの方法を5つ紹介します。
お店のイメージやメニュー表のスタイルによって、出来ることと出来ないことがあると思いますが、参考にして頂けたら幸いです。
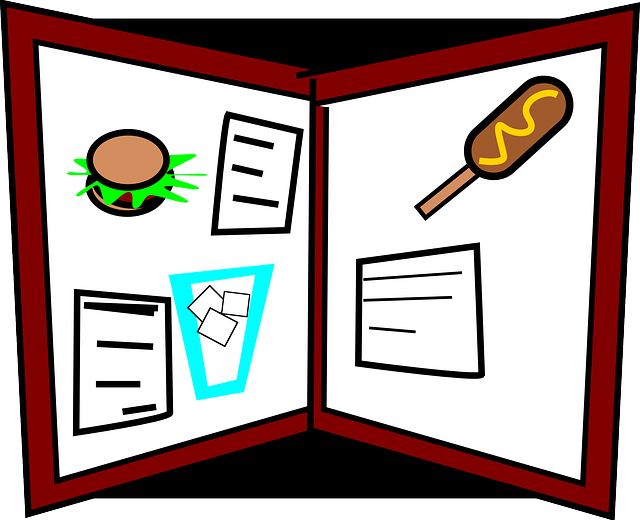
売れるメニュー表①『人気ランキング表示』
『注文数No.1!』
『肉料理部門2位!』
『現在人気急上昇中!』
のような言葉をタグ付けし、この店の何が売りなのか、何がよく食べられているのか、をわかりやすく明確にメニュー表で示します。
そうするとまず、冒頭のような不毛なやり取りがなくなります。
なにより、お客様はなんの圧力もなく、他の料理と見比べながら自分のペースで選択できます。
店側としても混雑時に説明にとられる時間が減るという大きなメリットもあるわけです。
そして意外にもこのランキングにお客様は、結構導かれるものです。
人間には『多くの人が支持しているもの』は『良いものに違いない』と思う心理作用があるからですね。
百貨店やネットショップでも
『1番売れています』
『累計○○個販売』
などの文字を見ると、なんとなく気になったり購入の選択肢に入ってくることがありますよね。
それと同じで、一目で人気度がわかると惹かれやすいのです。
メニュー表じゃなくても、ポップなどの掲示物で売れ筋商品のランキング表があっても良いですね。
私が1番おすすめしたい方法です。
売れるメニュー表②『おすすめ表示』
前述のランキング表示はそのお店のレギュラーメニューが対象になると思いますが、
『おすすめ表示』は、
・日替わりや季節メニューなどイレギュラーな料理
・レギュラーメニューだけどランキング上位ではないそこそこ人気の料理
を推すことができます。
『本日のおすすめ!』
『人気!』
『今だけ!』
こういうタグがついているだけで人は目が行きますからね。
また、
『ワイン好きに大人気!』
『迷ったらまずコレ!』
『辛党ご推薦!』
のように嗜好別にナビゲートできる書き方もおすすめです。
ただし、書きすぎ、推しすぎは逆効果です。
こちらの記事では推しすぎが逆効果になる人間の心理について解説していますので、よろしかったら参考になさってください。
ゴリ押し注意!推されると抵抗したくなる心理から考える販売・誘導テクニック。飲食店集客方法

 PR
PR売れるメニュー表③『サッと出せる、とりあえずの1品枠』
『とりあえずの1品』これも結構重宝されますよ。
サッと出せるような前菜、軽いつまみ、小鉢ものなどをまとめておくんです。
そこに『お待たせしません』というような文言を添えておくと、なお良いです。
お客様はみんな、待つのは嫌ですからね。
メイン料理を待つ間のつなぎ、箸休めに重宝されます。
特にお酒を頼まれるお客様は、とりあえず何かつまみたい…という方がわりと多いものです。
お通しがあればまた違いますが、近年はお通し不要論が勃発しているくらいですし、業態にマッチしないなどの理由も含め、お通しを採用していないお店も多いと思います。
そんなお店こそ、このようにサッと出てくる『とりあえずの1品』という枠の設置は大変有効です。
“かゆいところに手が届く” 計らいはお客様の心地よさを刺激しますよ。

お通し不要論についてはこちらの記事で詳しく書いていますのでよろしかったらご覧ください。
お通しはいらないんだけど…断れる?お通し代や席料、突き出しについてお話します。
売れるメニュー表④『迷えるお客様に、盛り合わせ枠』
前述の『とりあえずの1品』枠に続いてこちらは
『盛り合わせ』枠。
『本日の刺身 3種盛り』
『焼き鳥人気5本セット』
『おまかせチーズ盛り合わせ』
特に女性のお客様、ご新規様、グループのお客様、1品1品注文するのが面倒くさいお客様たちにとって、 1皿で数種類の味が楽しめるというのはとても気が利いたスタイルです。
しかも、セットや盛り合わせってだいたいちょっとは得だったりしますよね。
そこに魅力を感じるお客様も少なくないので、もしまだ、盛り合わせメニューがないということであれば、何か抱き合わせられるメニューで作ってみてはいかがでしょう。
わりと需要のあるスタイルなのでおすすめです。
売れるメニュー表⑤『料理名はわかりやすく完結に』
あまりに長かったり、ちょっと凝ったネーミングは、イメージを持たせるのにはとてもいいんだけど、お客様によってはわかりにくかったり、頼むのに恥ずかしかったりするんです。
『コラーゲンたっぷりクラゲの美肌サラダ』
『クラシックを聞かせてじっくり熟成させたビーフステーキ』
『森のキノコととろ~り卵のココット』
これ、実際に私が外食で遭遇した料理名です。
確かにイメージはまあまあ沸きますね。
でも、声に出して頼むのちょっと恥ずかしい時ありませんか?
「とろ~り」とかね。
省略して頼むことも出来ますが、丁寧に全て読み上げるお客様も多いものです。
タッチパネル注文のお店であれば、この点については問題ないのでしょうが、言葉の長さにも混乱の可能性があります。
長ければ長いほど情報がすんなり入ってこないお客様もいるものです。
ですので、文字に大小つけたり、色やレイアウトの工夫をしながら、
『メインタイトル+サブタイトル』
もしくは、
『メインタイトル+料理説明』
のように分けると良いですよ。
例えば先ほどの料理名の場合、
『クラゲのサラダ』~コラーゲンたっぷり美肌効果!~
『クラシックビーフステーキ』~モーツァルトを聞かせてじっくりねかせた上品な味わい~
『キノコのココット』~森のキノコととろ~リ卵のオーブン焼き~
といった感じです。
メインタイトルは、お客様にとにかくわかりやすく、言いやすい音で、完結に、をおすすめします。
そして、もうひとつ
『名物ノブちゃん焼き』
のような、お店のオリジナル度の高いネーミング。
一見、目を惹きますが、これは新規客には間違いなく疑問を抱かせてしまいます。
例えば、料理名の横に『店長ノブちゃんの秘伝タレに漬け込んだやきとん』
というように、どんな料理なのかイメージできるような補足を加えておくと大変親切ですね。
さて最後に、メニュー表やポップ作りに私もよく使う、コスパの良いラミネーターをご紹介しておきますね。
掲示のメニュー表など、ちょっと破けてたりシミがついてたりすると景観的イメージが悪いだけでなく、メニューが更新されていないような無気力感をお客様に与えてしまいます。
ラミネーターは掲示物を劣化や汚れから守るので屋外のポップなどにもおすすめです。
こちらはアイリスオーヤマのA3サイズ対応のラミネーター機です。
A3対応機種の中でもこれは結構安いほうで、操作は超どシンプル。(ラミネートするだけなのでむしろいろんな機能はいりません)
A3サイズまであったほうが何かと便利だと思いますが、A4サイズまでもう少し価格を抑えた機種もありますよ。
100μまで対応です。μ(ミクロン)はフィルムの厚さを表していますが、100μあれば掲示物の保護には十分です。
ちなみにフィルムは別売りですよ。
いかがでしたでしょうか?
メニュー表作りの参考にして頂ければ幸いです。
それ危険度高め!飲食店経営が勘違いしてはいけない3つのバイアス。当てはまったら潰れる危機
PR 店舗の集客にお困りなら無料で簡単にできるコチラへ!
WEB集客0円【エキテン】








